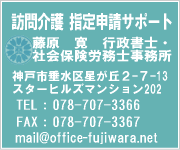「通院等のための乗車又は降車の介助」について
訪問介護において「通院等のための乗車又は降車の介助」(通院等乗降介助)を実施するには、道路運送法の許可・届出が必要となります。
1.「通院等のための乗車又は降車の介助」とは?
2.道路運送法の許可について
3.自家用自動車の有償運送事業許可
4.許可の申請について
「通院等のための乗車又は降車の介助」とは?
「通院等のための乗車又は降車の介助」とは、要介護者である利用者に対して、通院等のため、指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、自らの運転する車両への乗車・降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前・降車後の屋内外における移動等の介助、通院先や外出先での受診等の手続き・移動等の介助を行うことをいいます。
通院等の乗降介助を実施するには、道路運送法第4条の一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)の許可、同法43条の旅客自動車運送事業、あるいは、同法第79条の福祉有償運送事業の届出が必要となります。
さらに、道路運送法第78条の自家用自動車の有償運送の許可を受けることにより、指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、その所有する自家用自動車により、輸送を行うことが可能となります。
道路運送法の許可について
訪問介護事業所が、その訪問介護サービスと連動して、または一体となって輸送サービスを行う場合は、道路運送法の許可または登録が必要となります。
許可・登録にはどのような種類があるのでしょうか?
①一般乗用旅客運送事業許可(福祉輸送事業限定)(道路運送法第4条)
②特定旅客運送事業許可(道路運送法第43条)
③福祉有償運送事業登録(道路運送法第79条)
④自家用自動車の有償運送事業許可(道路運送法第78条)
訪問介護事業者が行う要介護者等の輸送については、①の道路運送法第4条の許可を取得することが基本となります。①は一般的に介護タクシー許可と呼ばれています。
NPO法人等であれば、一定の手続き・条件の下で、③の道路運送法第79条に基づく登録を受けることで、輸送サービスを行うことができます。
自家用自動車の有償運送事業許可
一般の自家用自動車は、原則として有償運送の用に供すことは出来ませんが、公共の福祉確保のためにやむを得ない場合で国土交通大臣の許可を得た場合は、例外的に自家用自動車(白ナンバーの車両)で有償運送を行なうことが出来ます。
その許可が、上記④の自家用自動車の有償運送事業許可(道路運送法78条)です。
この許可を取得することで、訪問介護員等が自己の車両により、要介護者等を有償で輸送することが可能となります。(運転者は、一定の条件の下で、第1種運転免許で輸送サービスを提供することが可能となります。)
ただし、自家用自動車の有償運送許可を取得するためには、事前に、訪問介護事業所などの指定(※)と、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)の許可を受けておく必要があります。
許可の申請について
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)の許可(介護タクシー許可)を取得するには、各地方運輸局で示している「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)の許可の申請に関する審査基準」をクリアしなければいけません。その上で、必要な書類を作成・手配して許可申請することになります。
自家用自動車の有償運送許可は、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)の許可取得後、必要な手続きを終えてから申請することになりますので、ご注意下さい。
通院等乗降介助をはじめるなら⇒【介護タクシー開業サポート】をご利用下さい。
お問い合わせ
大阪・兵庫・神戸での訪問介護の指定申請・許可取得は、お任せ下さい。当事務所では、地域の皆様が安心して訪問介護事業を開業できるよう全力でサポートさせて頂きます。
お問い合わせ先 : 藤原寛 行政書士・社会保険労務士事務所
TEL:078-707-3366
電話受付 平日 9:00~18:00
メールでのお問い合せ : 訪問介護指定申請サポート お問い合せへ